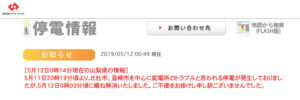「中学校適正配置推進事業」で統合の再検討を開始。市長は統合検討の前にやるべきことがあるのでは?
「中学校適正配置推進事業」ということで、少し前に教育委員会から議会へ説明がありました。
“適正配置”とされていますが、市長としては“統合”を前提としているといって差し支えない内容です。

(こんな素晴らしい景観、環境という強みを生かせば、子育て世代の移住者は今まで以上に増やせるはず)
なぜ4校案が進められなくなったのか、過去の答弁を抜粋します。
(H30第1回議会、堀内教育長答弁)
中学校の統合は避けては通れない課題であると認識しているところであります。 義務教育である中学校におきましては、生徒が集団の中で多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて一人ひとりの資質や能力を伸ばしていくといった、そのような目的が果たせるよう取り組んでいく必要がございます。しかしながら、中学校統合の検討を進めるにあたっては、行政が一方的に進める性格のものではないと考えておりますので、学校関係者や市民の皆さまから意見を伺いながら、議論を重ねてまいりたいと考えております。
(同、教育部長答弁)
北杜市といたしましては、市長の公約というようなことでございましたけども、4校案については理解をいただけない点もあるので、いったん白紙にということで、これについては事実、 白紙に戻った状態でございます。
今回議会の説明に使われた資料では次のような表現となっています。
中学校の統合については、平成26年2月に市立中学校統合計画(案)を策定し、学校関係者等から意見を伺ったが、4校案を進めることは難しいとしたところである。しかしながら、少子化に伴い生徒数が減少する中で、学校の適正配置は避けて通れない喫緊の課題であり、より良い教育環境を提供するため、適正配置について検討を進めることとした。
(課題)
生徒数の減少に伴う学校統合は喫緊の課題であるが、地域での説明会や意見聴取会などを通じて、地域性を考慮する必要性、通学への不安などさまざまな意見が寄せられた。今後は、中学校統合へ向けて、協議検討を進める必要がある。
このように、渡辺市長は中学校を統合することを前提としています。
ちなみに今回はどう議論を進めるのでしょうか。
まずは、
・何が理解頂けなかったのかを明確にすること
これを曖昧にするとまた理解をいただけない結果を招く可能性が高くなります。
その上で、
・渡辺市長が考える課題とは何かを明確にすること。
・それら課題を解決するためには統合しかないのか。統合以外の解決策はないのか。
これらについてクリアにする必要があるでしょう。
一部地域委員会での議論を聞きましたが、市民の間では統合に対する根強い反対意見があるとの理解です。
本当に統合は「避けて通れない」のでしょうか。
さまざまな技術が発達しています。そういった視点も加味して議論していただきたいと思います。
そして統合する場合は、
・どこを統合して、新しい場所はどこにするのか
という検討に移ります。
ここでも選択肢の比較検討が行われるのは当然で、曖昧にすると合意は得られません。
■
今後のスケジュール案としては次のように説明を受けています。
平成31年度(令和元年)
・小中学校適正規模等審議会を設置し、計画策定に向けた取り組みの進め方などを審議。地域での意見を踏まえつつ、8校区域ごとの意見を集約する中で、適正配置実施計画の見直しや統合計画の作成などについて協議検討を進める。
・各学校区において、中学校の統合について、経緯や課題等について説明会を開催する。
4月 小中学校適正規模等審議会の公募募集(募集してない?)
6月 委嘱 → 審議会開催スタート
令和2年度
・適正配置に向けた関係者(教員、PTA、学校評議員、地域関係者)を募り、地域における中学校のあり方や統合について意見をまとめる。
・ワークショップと審議会で審議した内容に基づき、適正配置実施計画見直し
令和3年度
・適正配置実施計画に対するパブコメを実施。
・中学校統合計画案の作成、パブコメの実施。
・中学校統合計画策定。
令和4年度
・4月に中学校統合計画を公表。
・5月〜説明会を実施。
■
統合により中学校の無くなる地域に子育て世代が移住して来てくれるハードルは高くなると考えるのが自然でしょう。
結果として地域が廃れる、といった懸念の声が過去の議事録にも当然ありました。
これからの何十年かを決める、とてつもなく重大な決定となります。
中学校の無くなる地域はどう街づくりをしていくのか、グランドデザインとセットであるべきです。
私はかねてより、統合議論の前にやるべきことがある、という立場です(※統合以外のソリューションがない場合)。
子育て世代が増えて、各学年2クラスになれば、地域から学校が無くなる統合の必要性は低くなるはずです。
市長は期限を設けて、各地域で本気で移住定住受け入れに取り組んでもらうことを提案すべきではないでしょうか。
良い意味での地域間競争であり、切磋琢磨です。場合によっては地域差が出て、統合やむなしとなるかもしれません。
そこまでやってはじめて自分の住む地域から中学校が無くなることを受けて止めることができると思います。
こういったプロセスを踏まないと、市民からの理解は得られないだろうと考えています。
(※繰り返しですが、あくまでも統合以外のソリューションがない、との結論が出た場合の話です)
加えて言えば、移住定住を推進しているにも関わらず、いつ何時隣に地上設置型太陽光パネルが敷き詰められるか分からない現状を改善するなど(これが理由で多くの移住希望者が二の足を踏んでいる)、市長はアクセルとブレーキを同時に踏んでいる状態を正していくことも重要です。
■
武川が自校式から給食センター方式へ移行する際の教育委員会の説明は丁寧さに欠け(質問にきちんと答えないなど)、指摘しても何度か改善されず驚かされたこと等は、以前ブログでご報告しました。
難しい仕事ですが今回はそのようなことが無いように、教育委員会の皆さんは覚悟を持って取り組んでいただきたいと思います。
期待しています!
■
本日は「開かれた北杜市政へ手をつなぐ市民の会」の皆さまにお声がけいただき、意見交換をさせて頂きました。
貴重な機会を作って下さいまして、誠にありがとうございました!
池田やすみち(山梨県北杜市議会議員)

■プロフィール■
池田恭務(いけだやすみち)
1973年5月1日生まれ(46歳)
1997年国際基督教大学(ICU)教養学部社会科学科卒
外資系コンサルティング会社等民間企業を経て、
渡辺喜美みんなの党代表秘書(公設政策秘書)。
2016年11月より山梨県北杜市議会議員。
会派無所属の会代表、経済環境常任委員会前副委員長、広報編集委員会副委員長。